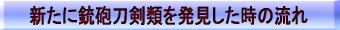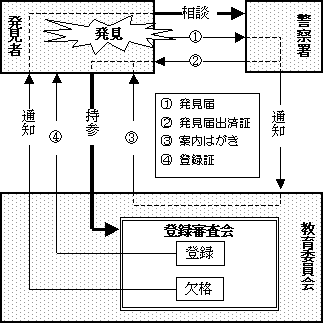新たに銃砲刀剣類を発見した場合
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月21日
銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されています。
所持禁止の例外の一つとして、同法同条第6号及び同法第14条により、「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所の所在する都道府県の教育委員会で登録することにより所持することができます。
- 発見された銃砲刀剣類に係る銃砲刀剣類登録証がない場合は、下記の手続きを行ってください。
- 発見された銃砲刀剣類に係る銃砲刀剣類登録証がある場合は、下記の手続きではなく、所有者変更届出書の届出を行ってください。
1.最寄りの警察署に、発見した銃砲刀剣類を持っていき、発見届を提出してください。
- 銃砲刀剣類発見届出済証が発行されます。紛失しないように大切に保管してください。
- 発見した銃砲刀剣類の所持を希望されない場合は、その旨を申し出てください。
2.県教育委員会からの「銃砲刀剣類登録審査会」開催案内に従い、審査会で審査を受けてください。
- 警察署で発見届を提出された方には、県教育委員会から「銃砲刀剣類登録審査会」開催の案内状を送付します(案内状は、審査会開催のおおむね2か月前までに発見届を提出された方が対象です。会場の都合上、直近の審査会に御案内できないことがあります。)。
- 案内状をお持ちでない方は、審査を受けることができません。
- 審査会に持参するもの(広島県開催の審査会の場合)
銃砲または刀剣類の現物、案内状、銃砲刀剣類発見届出済証、手数料(銃砲刀剣類1件につき登録申請手数料6,300円)
※手数料は審査を受けるための手数料です。登録できない場合でも手数料は返却できませんので、御承知おきください。
登録の基準
- 銃砲(銃砲刀剣類登録規則第四条第一項)
日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、次のいずれかに該当するものが登録の対象となります。
一 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌(がん)、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。) - 刀剣類(銃砲刀剣類登録規則第四条第二項)
日本刀であって、次のいずれかに該当するものが登録対象となります。(日本刀とは、武用または観賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施したものであり、やり、なぎなた、ほこ等を含みます。)
一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
二 銘文が資料として価値のあるもの
三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
3.審査会で登録可能と判断されれば、登録証が発行されます。(手続終了)
登録不可と判断された場合は、発見届を提出した警察署に取扱いを相談してください。