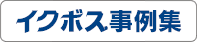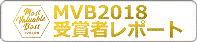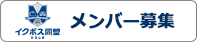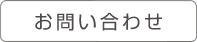青野氏×湯崎知事 特別対談~時代が求めるリーダー「イクボス」とは~
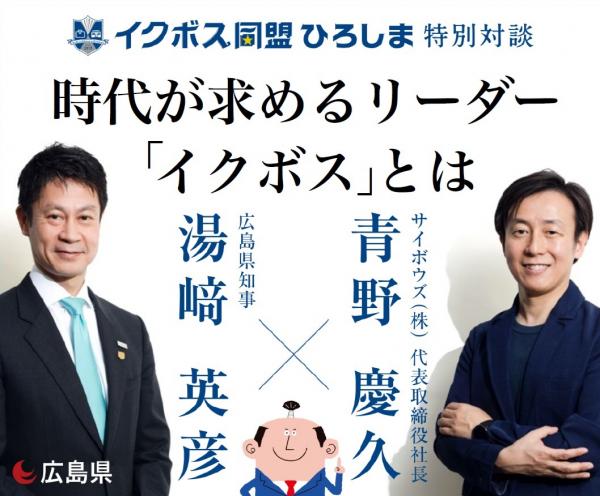
社内のワークスタイルを変革して業績を上げるとともに、昨今の「働き方改革」についても多くの提言をされている青野慶久氏。「イクボスミーティングひろしま」のために来広された青野氏と知事が今なぜ「イクボス」なのか、「イクボス」の真の意義について語り合いました。
いま、どうして「イクボス」なのか?
-最初に改めて「イクボス」について教えてください。
湯崎英彦知事(以下、湯崎)
イクボスとは社員のさまざまな立場を理解して、彼らの希望をなるべく叶えられるよう配慮できる経営者や管理職のことです。今の時代、少子高齢化などの影響もあって働き手はどんどん減っています。その中で社会の活力を維持するにはいろんな人が働ける環境をつくらなければいけない。つまり一人ひとりが活躍できる社会を目指していくことが必要になるんです。
-すでに人手不足などの弊害は出ています。
湯崎
広島県はそれに加えて、仕事も暮らしもあきらめずに楽しむ、「欲張りなライフスタイル」を掲げていますが、多くの人が生き生きと働ける環境をつくることは個人の幸せにもつながると思うんです。さらに個々人の生活が充実することでイノベーションやクリエイティビティも活性化すると考えています。狭い視点で仕事をしていても斬新なアイデアなんて出てこないですからね。そうした「社会も会社も個人も生き生きできる職場環境をつくること」はトップにしかできないので、そこでイクボスの出番というわけです。
青野慶久 代表取締役社長(以下、青野)
僕が働き方について考えるようになったのは、自社の社員の離職率があまりに高かったからなんです。それで会社を辞めたいという人たちに話を聞いてみたら、みんな事情が違っていて。「とにかくお金がほしい」という人もいれば、「お金はそこそこでいいから時間がほしい」という人もいる。「問題は勤務地」という人もいれば、「仕事の内容が大事」という人もいる。本当に多種多様で、それが衝撃だったんです。そこから「全員の希望を拾ってあげれば、みんなが幸せになれる会社になるんじゃないか?」と考えるようになって。個々人が持つ多様性をどのように組織で吸収できるかが企業戦略的に大事ということを理解しました。
「働き方改革=ただ労働時間を短くすること」という誤解
湯崎
さまざまな背景を持つ社員の中には「私は思いっきり働きたい」という人もいますよね。体を壊すほど働くのは論外ですが、「働きたい」と言ってるのに「仕事はやめて早く帰れ!」って止めさせるのもモチベーションが下がります(笑)。
青野
どうしても画一的に進めようとするのが日本人の悪いクセで。僕は「女性活躍」という言葉もあまり好きじゃないんです。だって女性の中には「私は専業主婦になりたい」という人もいるわけで、それなのに「女性もみんな活躍だ」って……「なんでむりやり私が活躍させられなきゃいけないの!?」ってなりますよ(笑)。どんな事象であれ、カテゴリーで考えず、常に一人ひとりと向き合うことが大事だと思います。

|
1971年生まれ。愛媛県今治市出身。大阪大学工学部 情報システム工学科卒業後、松下電工(現パナソニック)を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立。2005年4月代表取締役社長に就任(現任)。社内のワークスタイル変革を推進し、離職率を6分の1に低減するとともに、3児の父として3度の育児休暇を取得。2011年から事業のクラウド化を進め、2016年にクラウド事業の売上げが全体の50%を超えるまで成長。総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣官房の働き方改革プロジェクトの外部アドバイザーを務める。 |
湯崎
現在の社会変化に伴い、企業がイノベーションを起こし成長するためにも多様な価値観を受け入れる必要がある。組織が変わるには、組織のトップが意識を変え、率先して行動することが大事。
イクボスや働き方改革については、「ただ労働時間を短くすること」と誤解されているところがあります。
湯崎
働き方改革というと、何かと過労死の事件が取り上げられ、それが長時間労働の結果引き起こされたので、「とにかく労働時間を減らそう」という方向に向う動きがあります。もちろん最低限の配慮として健康を害するほど仕事をすることは避けなければいけませんが、人は究極的に自分が幸せになるために仕事をしているわけです。何に幸福を感じるかは人それぞれなわけで、一律に対応するのではなく、そこを認めてあげることが重要になると思います。
青野
そうなんです。確かに過労死の事件は悲しいことですが、だからといって「じゃあ、何があろうと全員残業禁止!」というのはこれはこれでパワハラですよ。
「イクボス」は成長を遂げるための経営戦略である
-「イクボス」は社員に寄り添う取組である一方、成長を遂げるための経営戦略として捉えている点も新鮮です。
湯崎
我々の課題は「この人口減少社会の中で、どう豊かさを失わず安定的に成長できるか?」ということなので効果という部分は非常に重要です。それをやることで社会が豊かにならなかったら何の意味もないですよ。

| 1965年生まれ。広島市佐伯区出身。東京大学法学部卒業後、通産省(現経済産業省)入省。スタンフォード大学経営学修士取得。同省退官後、株式会社アッカ・ネットワークスを設立し、代表取締役副社長等を歴任。2008年に同社取締役を退任し、翌年広島県知事選挙に出馬して当選。2010年には都道府県知事として初めて育児休暇を取得、2015年には「イクボス宣言」をするなど、働き方改革に積極的に取り組む。 |
青野
サイボウズでも働き方改革を行ったことで売上げは上昇しました。知事もおっしゃいましたが、豊かさを求めようとすると仕事の効率は自然と上がっていくんです。個人が幸福を追求できる状況をつくることで社員のモチベーションは上がるし、ダイバーシティ(多様性)が生まれるのでイノベーションも起きやすいし、結果的にロイヤルティ(会社への忠誠度)も上がる。経営的には“一挙3得”くらいありますよ。経営者の中には「個人の自由なんて認めたら会社の規律が乱れて業績が下がるに決まっている」と言われる方もありますが、今後はそのやり方の方が業績は下がっていくと思います。
究極の『公平』とは、一人ひとりを大切にすること
湯崎
講演の中で青野さんは「人はみんな『公平』じゃない」とおっしゃってましたが、あれは非常に大事ですね。今の世の中は「すべての人は『公平』であるべき」という意見が主流だけど、一人ひとり見てみればみんな違うわけです。置かれた状況も違うし、夢も違う。その違いがちゃんと認められ、各自に合った働き方ができ、きちんと評価されることが究極の『公平』なんじゃないでしょうか。
青野
僕はよくこんな例えをするんですけど、ここに3人の人がいてホールケーキが一つあるとする。『公平さ』を訴える人は単純に3等分しようとする。だけど一人ひとりに「ケーキ食べたい?」と尋ねたら、「ダイエット中で食べたくない」という人もいるかもしれない。そういう人に有無を言わさず1/3を食べさせるのはありがた迷惑ですよね。3人に意見を聞いてみたら、もっと適切な切り分け方や、よりハッピーになれるシナリオがあるはずなんです。問答無用で3等分するのは思考停止でしかないと思いますよ。
キーワードは「一人ひとりを大事にする社会」ということかもしれませんね。
湯崎
個性を大事にするというのは、今の日本がもっとも苦手としているものです(苦笑)。
青野 これまでは“みんな均一、みんな横並び”というやり方でうまくいってたんです。工業化社会は全員が朝9時に出勤して、まじめに働く会社が勝つっていうシステムですからね。だけど、そのやり方だけだともう人件費の安い国に負けてしまいますよ。
一番避けるべきは“画一的”。多様性を認め、豊かな社会へ
湯崎
そう。社会環境が変わりつつあるから、新しいシステムを作っていかなきゃいけないんです。今はそういう産みの苦しみの真っ最中。ただ、だからといって「仕事の量を減らして私生活を充実させよう!」と押し付けるのではなく、すべての選択が可能ということが大事ですよね。仕事100%の人を否定するのではなく、そういう人も認めつつ、「私はこうしたい」「私はこれがいい」という意見が許容される柔軟なシステムにしていきたいと思います。
青野
うちの会社は複業もOKにしたんですけど、そうしたらサイボウズにいながら農業に取り組む社員が出てきたんです。そこでは自然と“IT×農業”というオープン・イノベーションが発生していて、さらにそういう人材がいることで他のスタッフが刺激を受ける好循環が起こっています。

湯崎
多様性というのは経済活動だけじゃなく社会全体の豊かさにつながると思うんです。それがイノベーションを生んでいく素地になる。やっぱり一番避けるべきは、“画一的”ってことなんですよ。
青野
会社のボリュームゾーンにいない“変わり者”みたいな人が実は一番イノベイティブな位置にいたり、あるジャンルにおいての最先端に立っていたりしますからね。そういう人を排除してしまうのは企業としても社会としてももったいないです。
いま広島の多くの企業が抱えている問題とは?
青野
ところで知事は広島県内の労働環境において、どこに大きな問題を感じておられますか?
湯崎
一番は事業継承でしょうね。広島の7割の企業は事業継承に問題を抱えているというデータが出ています。それは裏を返せば、古い価値観の世代と新しい世代がうまく結びついてない場合があるのでは。中には、今の経営者が「とにかく闇雲に働く」という自分の成功体験からなかなか脱却できず、それを若い社員に押し付けてソッポを向かれているというケースもあると聞きます。自分の価値観を変えるのは勇気のいることですが、今の状況に気付いた経営者からいかに変革していけるか。そういうイクボスを応援する活動を、これからも広島県は続けていきたいと思います。
青野
会社も地域も風土というのが大事ですからね。湯崎さんを先頭にそういう取組をされている広島県は、一経営者から見ても魅力的に映ります。サイボウズも来年広島に事務所を立ち上げる予定ですが、僕らが広島に来ることでみなさんの働き方に対する意識を刺激して、新しいムーブメントを起こしていければと思います。
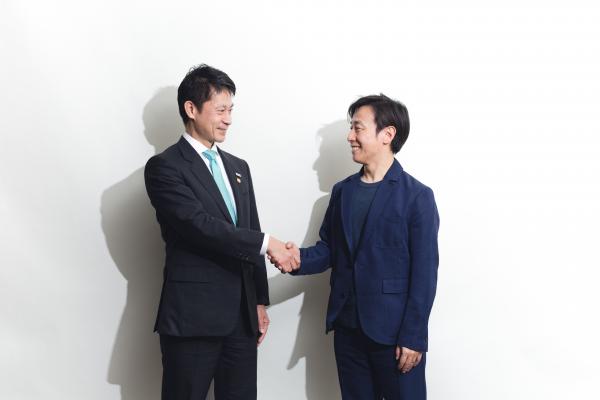
今回の対談は、イクボス同盟ひろしま初の成果発表会「イクボスひろしま」を記念して実施しました。
青野氏による基調講演の様子や、同盟メンバーによる成果発表の様子がダイジェストで掲載してあります。