本文
令和7年1月20日(月)に、菅田委員が福山市立想青学園を訪問しました
福山市立想青学園は、広島県福山市沼隈町に位置し、内海小学校、内浦小学校、能登原小学校、常石小学校、千年小学校、内海中学校、千年中学校の7校が一つになり、2022年4月に開校した義務教育学校です。
義務教育学校とは、小学校(前期課程)から中学校(後期課程)までの9年間の教育を一貫して行う学校のことで、想青学園では、柔軟なカリキュラム編成や前期課程での教科担任制、新教科の創設などの取組も行われています。
また、校名の「想青」には、子どもたちに未来を切り拓いてほしいという願いと、未来に向けて育っていく学校にしていくという想いを込められているそうです。
今回は、校舎内を案内していただきながら、前期課程と後期課程の授業の様子を見せていただきました。
想青学園の校舎は、前期課程と後期課程の教室が一体的に配置され、職員室や体育館は2階にあります。広い廊下に面した教室はガラス張りになっており、とても開放的です。
普通教室や特別教室を各階に配置することで、異なる学年の交流が生まれます。上級生が下級生の手本となり、上級生は下級生からの憧れの対象となることで、上級生と下級生が互いに良い影響を与え合う環境となっているようです。

校舎内には各教科のブース等のフリースペースがいくつも設けられ、児童生徒が自由に利用できるようになっていました。
教室外のスペースを充実させることで、児童生徒が自分たちで学べる場を設定しているとのことです。

次に図書室を見せていただきました。
9つの学年の児童生徒が利用する図書室は広々としており、カーペットが敷かれた読書スペースを配置したところ、後期生が前期生に読み聞かせをするなど異学年交流が図れる空間になったそうです。

また、図書室の奥にはデジタルラボという部屋がありました。ここには、動画編集等ができる高性能パソコンや3Dプリンタが設置されています。
IT機器は、地元の専門家の方などが使い方などを教えてくださっているとのことで、地域の方が積極的に学校運営に関わってくださっているそうです。

ほかにも、校舎内には地域と関わる機能をもつふれあいルームやランチルームなどが設けられています。
続いて、前期課程の3年生(小学3年相当)の理科の授業を視察しました。

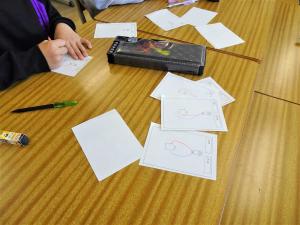
授業では、日常生活の中の事柄の中から「なんでだろう」という疑問をもち、自分で考え、確かめるということを大切にしているそうです。
次に、後期課程8年生(中学2年相当)の社会の授業を見せていただきました。
日本の各地域について、各生徒が探究テーマを決め、調べた結果をまとめてポスター発表するもので、2学期から取り組んでいます。
探究テーマには、
・【関東地方】東京におけるヒートアイランド現象による影響は年々どのように変化しているのか。また緑を増やすなどの取り組みによる成果はあるのか
・【九州地方】阿蘇山のカルデラに住む人々の生活の暮らしと工夫
・【中国・四国地方】現在の瀬戸大橋が果たしている役割は?
などがあり、それぞれの生徒が興味や疑問をもったテーマを設定していました。
「地域性や他地域とのつながりを活かすとともに、革新的なアイデアや技術を活用することによって持続可能な社会を構築できる」という視点から、各地域と福山市との比較や現状などを一人一台端末などを使って調べ、先生にアドバイスなどを受けながらグラフなどの図表を用いてポスターにまとめており、発表時には同じグループの生徒からの質問にもしっかりと答えていました。
菅田委員は「参考文献や参考サイトなどもまとめられており、大学での発表にも似ている」と感想を述べておられました。


最後に、教員の方にお話を伺いました。
教科書の枠の中だけでなく、子どもたちが持っている「やりたい」「知りたい」という思いをより一層大切にされており、子どもたちが知っていることを使って考えると、分かることがたくさんあるという感覚を授業の中で積み重ねていけるように取り組んでおられるそうです。
また、教職員が授業実践力を高めるために研修を受講したり、国際バカロレアの学びを実践している広島県立叡智学園を訪問し、授業づくりのヒントをもらっているとのことでした。

想青学園では校区の歴史・文化、産業、自然等を素材に、児童生徒の発見や疑問に応じて柔軟に展開する探究学習(SOSEI学)にも取り組んでおり、今回の視察を通じて、児童生徒は整備された学習環境のもと、地域とも深く関わりながら多くの学びを得ていると感じました。










