本文
令和6年度地域課題対応研修支援(訪問型研修)報告
研修の様子
市町の研修担当者と連携・協働し、市町が実施する地域課題に対応した研修等の企画・運営を支援しています。
支援した研修の様子の一部を紹介します。今後の研修事業の企画・立案の参考にしてください。
| 市町 | 関係職員等研修 | 社会教育委員研修 | その他 |
|---|---|---|---|
| 呉市 |
まちづくりセンター職員研修(中級編) まちづくりセンター職員研修(初級編) |
||
| 竹原市 | 社会教育委員研修会 [8月1日(木曜日)] |
||
| 尾道市 |
公民館長研修会 |
社会教育委員研修会 |
地域コーディネーター研修 |
| 東広島市 |
社会教育関係職員研修会(1) |
||
| 廿日市市 | 市民センター所長研修 [4月19日(金曜日)] |
親プロファシリテーターフォローアップ&交流会 [1月29日(水曜日)] |
|
| 安芸高田市 | 社会教育指導員研修会 [12月12日(木曜日)] |
||
| 府中町 | コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に関わる研修会 [8月19日(月曜日)] |
||
| 熊野町 |
社会教育委員会 |
コミュニティ・スクール連絡協議会 [6月27日(木曜日)] コミュニティ・スクール実践交流会 [12月12日(木曜日)] |
|
| 世羅町 |
自治センタースタッフ研修会 |
||
| 広島矯正管区 | 再犯防止×地方創生政策ワークショップ研修 [1月29日(水曜日)] |
廿日市市
市民センター所長研修
研修のねらい
○生涯学習とまちづくりの拠点である市民センター業務に携わる所長の専門性の向上を図る。
受講者
市民センター所長、廿日市市まちづくり支援課職員等(23名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 4月19日(金曜日) 15時00分~17時00分 |
○講義 |


※広島修道大学人文学部山川教授の講義では、廿日市市の生涯学習・社会教育の現状をふまえて、これからの廿日市市市民センターの役割についてたくさんの御示唆をいただきました。講義の中では、意見交換の時間もあり、地域に学習活動や学ぶ場があることの意義について小グループで考えたり、日々の実践を振り返って学びを地域づくりにつないでいるか意見交流を行ったりしました。
※県立生涯学習センターの事業の1つ、「広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト」(通称:ひろプロ)」について、説明を行いました。昨年度までこの事業に取り組んだ他市町の職員のコーディネーターの実際を紹介しました。参加された皆さんに、これからの市民センター職員として求められる役割や資質・能力について事業説明を通して考えていただきました。
親プロファシリテーターフォローアップ&交流会
研修のねらい
〇「「親の力」をまなびあう学習プログラム(以下、「親プロ」)」のメインファシリテーターとして、展開例の作成、実践することで、これからの活動への意欲を高める。
〇ファシリテーター同士の親睦を深め、繋がりを作る。
受講者
廿日市市の「親プロ」ファシリテーター、廿日市市教育委員会生涯学習課職員等(6名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 1月29日(水曜日) 13時30分~16時00分 |
○報告 ○フォローアップ研修 ○交流会 |

報告では、廿日市市教育委員会生涯学習課の職員より、今年度開催した講座の報告及びホームページやチラシの紹介がありました。昨年度「親プロ」ファシリテーター養成講座を受講され、新米ファシリテーターとなった方が、昨年度から少しずつ活動されていることや、今年度は昨年度より実施講座回数が増加したこと等を報告していただきました。
フォローアップ研修では、プログラム27についてベテランファシリテーターと新米ファシリテーターがペアを組んで展開案を作成し、それぞれ違うグループの方の前で、メインファシリテーター体験を行いました。今回は同じプログラム27を取り上げましたが、各ペアで工夫されており、タイムマネジメントや声掛けの仕方等、改めて学ぶことができました。
最後の交流会では、ファシリテーターとして心がけていることについて意見交流を行い、ファシリテーターとしての意識を高めたり、ファシリテーター同士の横の繋がりを作ったりすることができました。
東広島市
社会教育関係職員研修会(1)
研修のねらい
○多様化、高度化する市民の学習ニーズや社会の変化に対応するために必要な知識、技能等について計画的、継続的に研修を実施し、職務の専門性を発揮できる社会教育関係職員の資質・技能の向上(人材育成)に努めるとともに、関係職員間のネットワークの構築を図り、生涯学習の振興、社会教育の推進に資する。
受講者
東広島市地域センター職員、東広島市教育委員会生涯学習課職員等(41名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 5月24日(金曜日) 13時45分~16時00分 |
○行政説明 ○講義 |



※講師の中村氏から、前任地である浅原市民センターで取り組まれた「広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト」(通称:ひろプロ)」での実践を発表していただきました。
※参加者から、次のような感想をお聞きしました。
・「あさはらビジョン」について知り、地域といかにつながるか、いかに関わりを持ち連携していくか、一人一人が自分事として考えていくことの大切さを学んだ。
・「あさはらビジョンづくりワークショップ」の考え方を聞き、地域住民の方の話を聞きながら、自分たちの地域が「住みたい地域」になるよう、人づくり・仲間づくりをすることが必要だと思った。
社会教育関係職員研修会(2)
研修のねらい
○職務上必要な学習プログラムの企画・立案・評価に関する能力の向上を図る。
○主催講座等の情報を交流して、今後の講座の企画・立案・評価へつなげる。
受講者
地域センター職員、生涯学習課職員等(15名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 7月5日(金曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義・演習 |




講義の前半では、生涯学習・社会教育の基本事項をはじめ、国や県、東広島市の動向や施策について理解を深めました。
講義の途中では、創造的な共創の場を生み出す手立てとして、円形の段ボール紙にクラフト用紙をのせて自分のアイデアを書いた後、「企画・挑戦してみたい事業(講座)」についてグループで話し合った内容などを交流しました。
講義の後半では、学習プログラム作成のポイントについて整理し、その後、これまでに実施した事業についてチェックシートを活用して振り返り、改善案を交流しました。
受講者からは、「どのように講座や事業を企画・立案していけばよいかが分かった。」、「自分でもやってみたい講座がたくさんあり、みなさんの意見を参考にしていきたい。」、「研修を通して横のつながりができたので、事業を企画・立案する際には一人で悩まず相談してみたい。」といった感想が聞かれました。
社会教育関係職員研修会(3)
研修のねらい
○多様化、高度化する市民の学習ニーズや社会の変化に対応するために必要な知識、技能等について計画的、継続的に研修を実施し、職務の専門性を発揮できる社会教育関係職員の資質・技能の向上(人材育成)に努めるとともに、関係職員間のネットワークの構築を図り、生涯学習の振興、社会教育の推進に資する。
受講者
東広島市教育委員会生涯学習課職員、東広島市生涯学習センター職員、東広島市地域センター職員、東広島市教育文化振興事業団職員等(65名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 11月22日(金曜日) 14時00分~16時15分 |
○説明 ○講義 |



講義では、ひとづくり、つながりづくり、地域づくりの好循環を創るための学びのデザインについて、県内外の取組も紹介していただきながら、学習支援者の役割について学びました。
グループワークでは、各地域で展開している事業やプログラムについて交流し、次年度以降の取組に向けて成果や課題を共有しました。
熊野町
コミュニティ・スクール連絡協議会
研修のねらい
○コミュニティ・スクールの取組を充実させるため、関係者の理解促進と学校運営協議会委員等の育成及び連携を図り今後の取組の充実につなげる。
受講者
学校運営協議会(コミュニティ・スクール)委員及び関係教職員、熊野町教育委員会事務局職員
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 6月27日(木曜日) 14時00分~16時00分 |
○情報提供・講義 |
情報提供・講義では、県内のコミュニティ・スクールや地域学校協働活動の取組事例について紹介しながら、それぞれの取組や活動のポイントについて理解を深めていただきました。
協議では、学校運営協議会ごとに、各学校のシラバスを見ながらどのような連携・協働ができるか話し合ったり、既に行っている活動や取組についてこれからどのようによりよくしていくか話し合ったりしました。それぞれの学校の特色を生かして、参加された皆さんで熱心な協議が行われました。
コミュニティ・スクール実践交流会
研修のねらい
○コミュニティ・スクールの取組を充実させるため、自立的な地域学校協働活動を展開していく。
受講者
学校運営協議会(コミュニティ・スクール)委員及び関係教職員、熊野町教育委員会事務局職員
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月12日(木曜日) 14時20分~16時30分 |
○実践発表 |


実践発表では、町内4つの小学校と2つの中学校のコミュニティ・スクールの実践発表が行われました。各校の校長先生や担当教員だけでなく、学校運営協議会委員の方も発表者となり、それぞれの学校の特色を生かした実践発表が行われました。
協議では、それぞれの学校の発表を聞いて、学校ごとに、教員と地域の方で熱心に意見交流が行われました。どの学校も前向きに、そして意欲的に今後の自校の取組について協議されていました。
交流会のまとめとして、今後さらに学校と地域の連携を深めていくために、学校の教職員と地域の方が目的やビジョンを共有し、連携・協働を進めていくことが重要であると、広島県教育委員会よりお伝えしました。
社会教育委員会
研修のねらい
○ひろプロ支援事業の趣旨・意義・効用を簡潔に説明することにより、社会教育委員が熊野町で実施中の事業の理解を深めるため。
参加者
熊野町社会教育委員、熊野町教育委員会事務局職員(18名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 1月30日(木曜日) 19時00分~20時30分 |
○講義「広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト(ひろプロ)について」」 |
講義では、広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト支援事業」(以下、ひろプロ)について、事業が求められる背景や概要について説明しました。国の答申や県の教育大綱で示されていることをもとに、公民館等が多様な主体と連携・協働して、地域課題を解決する学びの場を創出するとともに、学びを通じた地域づくりの活動を一層促進していくための拠点として重要な役割を果たせるように、生涯学習センターが支援を行っていることをお伝えしました。
その後、東防災交流センターの事業の取組や進捗について、センター長から説明が行われました。また、横展開を行っている、熊野町公民館の館長からも、ひろプロの考えをふまえた現在の取組について説明が行われました。
社会教育委員の皆様からは、「ポイント制度など、地域住民に参加してもらう工夫を考えてみてはどうだろうか。」、「こういった素晴らしい取組をぜひ地域住民に積極的に発信してほしい。」など、地域住民が主体となって参画するための意見が出されました。
熊野町のこれからの社会教育について考える、充実した会議となりました。
竹原市
社会教育委員研修会
研修のねらい
○国や県、市の動向を踏まえて、竹原市の社会教育委員の役割について理解する。
○竹原市の社会教育委員として、何ができるのかを考え、今後の活動や取組の方向性を検討する。
受講者
竹原市社会教育委員、竹原市教育委員会文化生涯学習課、竹原市地域づくり課職員等(12名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 8月1日(木曜日) 14時40分~15時40分 |
○講義・意見交流 |



竹原市社会教育委員会議に続いて、社会教育委員の研修会として、講義と意見交流を行いました。
講義では、第4期教育振興基本計画における国の教育全般の施策の方向性を確認しました。その後、県や市のビジョン等に沿って、竹原市の社会教育委員に求められていることやその役割について整理しました。
講義の中では、岡山県や長野県岡谷市の社会教育委員の取組を事例として取り上げ、活動のポイント等について説明を行いました。
その後の意見交流では、円形の段ボール紙にクラフト用紙をのせて自分の考えを書いた後、「竹原市の社会教育委員として取り組んでみたこと」についてグループで話し合った内容などを交流しました。
府中町
コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に関わる研修会
研修のねらい
○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、地域・学校の団体等がつながり、共通の目的や課題の元に連携して活動することで、地域と学校のつながりを強化させる。
受講者
学校運営協議会委員、教職員、コミュニティ・スクールサポーター、府中町家庭教育支援チームくすのき及び親プロファシリテーター、放課後子供教室ボランティア、行政職員(36名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
|
8月19日(月曜日) |
○講義 ○グループワーク |


前半は、「学校と地域の連携・協働の必要性」「コミュニティ・スクールと地域学校協働とは何か」「一体的推進のよさ」について講義をしました。コミュニティ・スクールの仕組みを活用して、地域学校協働活動を充実させることで、子供たちの幸せや生きがい、そして、地域や社会全体の幸せや豊かさの実現を目指すことについて、県内の事例を紹介しながら学びを深めていただきました。
後半は、3回のグループワークを通して、参加者の日常の活動報告や情報交換を行いました。1回目のグループワークは、同じ学校に所属する方々で、自校で行っている活動の共有を行いました。2回目のグループワークでは、違う学校に所属する方々で、それぞれの学校で行っている活動について、情報交換を行いました。3回目は、1回目と同じグループに戻って、他校の実践を共有したり今後の自校の活動に生かしたいことを協議したりしました。
尾道市
公民館長研修会
研修のねらい
○生涯学習・社会教育について国の動向を知り、ウェルビーイングの考え方を踏まえた施設や施設職員の役割について理解を深める。
受講者
尾道市公民館長(28名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 9月25日(水曜日) 14時00分~15時00分 |
○講義 「公民館とウェルビーイング」 広島県立生涯学習センター 社会教育主事 杉原 直樹 |
「教育振興基本計画から考えるウェルビーイング」「那覇市若狭公民館の事例に見る公民館とウェルビーイング」という構成で講義を行いました。
前半の「教育振興基本計画から考えるウェルビーイング」では、教育における国の方向性やそのコンセプトである日本社会に根差したウェルビーイングの向上について、例示を交えながら理解を深めました。
後半の「那覇市若狭公民館の事例に見る公民館とウェルビーイング」では、平成29年度第70回優良公民館表彰にて最優秀館を受賞した沖縄県那覇市にある若狭公民館の事例を参考に、公民館の取組とウェルビーイングのかかわりについて学びました。
参加者の声より
・研修の度に良い話を聞いて、理想はあるが、地域の環境や住民の年齢層などから難しいと感じることが多い。
・今、自分がやってみようと考えていることに対して少し具体が見えてきた気がします。
・ウェルビーイングの視点から日々の活動を見て、取り組んでいきたい。
社会教育委員研修会
研修のねらい
○社会教育委員が、教育振興基本計画の中にもあるウェルビーイングについて学び、意見交換をすることで、相互の連携を深める。
受講者
尾道市社会教育委員、行政職員(14名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 11月12日(火曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義 |



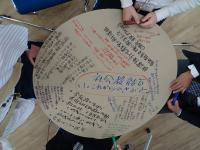
前半の講義では、社会教育委員の役割や意義について、社会教育法をもとに再確認しました。また、令和5年6月に閣議決定された、「第4期教育振興基本計画」について、2つのコンセプトの「持続可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」を確認し、そのための目標や施策、施策の柱など、国の新しい方向性についてお話しました。特に、「ウェルビーイング」については、中央教育審議会等で議論されたことをもとにしながら、基本的な考え方についてお話しました。
後半の演習では、グループごとに「えんたくん」を活用しながら、意見交流・協議を行いました。社会教育委員の方々の所属されている団体や活動していることを出し合い、課題を共有しました。その後、その課題等を解決していくために、社会教育委員としてできることについて協議しました。話合いはとても活発に行われ、社会教育委員の皆さんから、たくさんのアイディアが出されました。尾道市の人づくり、つながりづくり、地域づくりに向けて、地域のリーダーとして、活躍されることを期待しています。
地域コーディネーター研修
研修のねらい
〇コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進の担い手である地域コーディネーターに対して研修を行う。
〇コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進のために必要な基礎的知識を学び、資質の向上を図る。
〇他の地域コーディネーターと情報交換し、多くの手法に触れると共に後に活かせるつながりづくりを行う。
受講者
尾道市地域コーディネーター、行政職員(12名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2月7日(金曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義 |


講義では、コミュニティ・スクールを活用した事例を取り上げながら、地域学校協働活動コーディネーターの役割と意義について説明しました。学校と地域をつなぐ要となる人材として、「関係構築のスペシャリスト(つなぐ)」、「活動のプランナー(つくる)」、「地域資源の発掘・活用プロデューサー(活かす)」としての役割が期待されることをお伝えしました。
事例発表では、同じ市内の瀬戸田コミュニティ・スクールの取組事例について、瀬戸田小・中学校の地域コーディネーターが発表しました。どのようなことに留意しながら取組を進めているか、具体的な説明がありました。
その後のグループワークでは、日々の活動について情報交流を行いました。同じ市内の地域コーディネーターの方がどのようなことをしているか、互いの活動を知ることで、今後のそれぞれの取組の参考にすることができました。
世羅町
自治センタースタッフ研修会
研修のねらい
○国や県、町の動向を踏まえて、世羅町の自治センターの役割を理解する。
○各自治センター職員の交流を図り、今後の事業や取組の参考となる情報を共有する。
受講者
世羅町自治センター職員、世羅町企画課職員等(15名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 11月29日(金曜日) 13時30分~16時00分 |
○講義 ○意見交流 |




世羅町内には13の自治センターがあり、各地域で事業を推進されています。
前半の講義では、「第4期教育振興基本計画」をはじめとする国の動向や県の「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」、「教育大綱」等で生涯学習振興・社会教育行政に係る基本事項や動向を確認しました。また、世羅町自治センター設置条例等を参照し、自治センターに求められている役割についても確認しました。
後半の意見交流では、「世羅町の自治センターの職員として取り組んでみたいこと」のテーマのもと、グループで話し合った内容などを交流しました。
安芸高田市
社会教育指導員研修会
研修のねらい
○職務上必要な学習プログラムの企画・立案・評価に関する能力の向上を図る。
○主催講座等の情報を交流して、今後の講座の企画・立案・評価へつなげる。
受講者
安芸高田市社会教育指導員、安芸高田市教育委員会生涯学習課職員等(5名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月12日(木曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義(1) ○交流(1) ○講義(2) ○交流(2) |





前半の講義では、「第4期教育振興基本計画」をはじめとする国の動向や県の「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」や「教育大綱」等で生涯学習振興・社会教育行政に係る基本事項や動向を確認しました。そして、「安芸高田市教育大綱」や「第4次安芸高田市教育振興基本計画」をもとに、市の生涯学習施策の動向や方向性等について確認しました。
その後の意見交流では、ひとづくり、つながりづくり、地域づくりに係り、実際に取り組んでいる事業について、課題や悩み、改善策等について交流しました。
後半の講義では、学習プログラム作成のポイントについて整理し、その後、これまでに実施した事業についてチェックシートを活用して振り返り、改善案を交流しました。
呉市
まちづくりセンター職員研修(中級編)
研修のねらい
過去の事例をもとに、まちづくりセンター職員に求められるスキルとして、講座企画等の知識の習得や判断基準を学び、実務に結びつける。
受講者
呉市まちづくりセンター職員、呉市地域協働課職員(15名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月19日(木曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義 ○講義・演習 ○講義・演習 |
| 1月22日(水曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義 ○講義・演習 |



<第1回>
「学習プログラムについて」では、まちづくりセンターで実施されている講座は、市の取組の一環として行われていることや、目的や目標をもとにどういった学習成果を得ようとしているのかを明らかにしていくことの大切さについて確認しました。
「地域分析と学習課題」では、地域資源(ひと・もの・こと)にはどのようなものがあるか、地域の課題(個人の要望・社会の要請)にはどのようなものがあるかを分析し、学習課題を設定していくことを確認しました。また、これらに基づいて、現在勤務しているまちづくりセンターで取り上げる学習課題を設定する演習も行いました。
「学習目標の設定」では、学習の目的を具体化するための学習目標(知識・技能・意識)について確認しました。学習者にどのような知識や技能を獲得してほしいのか、また、どのように意識を変えていくのかを考えながら、実際に学習目標を設定する活動も行いました。


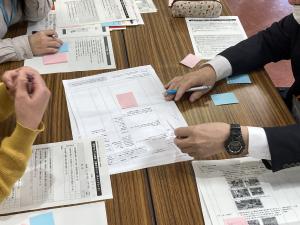
<第2回>
「学習プログラム作成のポイント」では、第1回の研修を踏まえながら、学習成果の活用を促す学習プログラムを編成することの大切さについて伝えました。
「学習プログラムの評価」では、評価の対象や時期によってさまざまな評価があることや、PDCAを意識してプログラムの改善につなげることについて伝えました。
「学習プログラムのリデザイン」では、参加者が各自で持参した学習プログラムについて、チェックシートをもとにして自己評価したり、グループ内で交流して改善案を提供し合う活動を行いました。その後、これらの改善案をもとに学習プログラムのリデザインも行いました。
全2回の研修を通して、「研修を受けることは、本当に大事だと思います」「他のまちづくりセンターの方の話を聞くことで気付きがあり、とても勉強になった」「PDCAを実践していきたい」といった感想がありました。
まちづくりセンター職員(初級編)
研修のねらい
「生涯学習」や「社会教育」についての用語解説や関係職員に求められる役割等の基本的な事項を理解する。
受講者
まちづくりセンター職員、生涯学習センター職員、地域協働課職員(18名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月24日(火曜日) 14時00分~16時00分 |
○講義 ○事例発表 ○演習 |
| 1月31日(金曜日) 14時00分~16時00分 |
○演習 ○講義 |


<第1回>
講義では、まず生涯学習の基本事項や現状について、「生涯学習に関する世論調査」をもとにお話しました。そして、社会教育の意義と役割について確認しました。また、令和5年6月に閣議決定された、「第4期教育振興基本計画」で示された、「ウェルビーイング」の概念についておさえました。
その後、呉市下蒲刈まちづくりセンターの職員の方に事例発表をしていただきました。地域住民の「学びの機会」を確保し、地域づくりの拠点として子供の居場所づくりの取組について紹介をしていただきました。
演習では、「えんたくん」を使って、「まちづくりセンターの職員としてできること」についてグループで意見交流を行いました。日常の取組の紹介や課題、悩みを共有しながら、これからできることについて意見や考えを共有しました。情報交換の場となり、皆さん、熱心に協議を進めていらっしゃいました。



<第2回>
演習は、まちづくりセンター職員に求められる資質・能力の向上に向けて、特に、ファシリテーション能力について体験的に学ぶことをねらいとして行われました。はじめは、「クイックチェック」や「バースデーチェーン」など、場の雰囲気や参加者の緊張感を少しずつ和ませ、関係づくりを行っていく様々なアイスブレイクを行いました。その後は、グループで課題解決にあたるワークに取り組み、他者とコミュニケーションをとりながら、相互交流がスムーズにできるようになるにはどうしたらよいか、体験的に学びました。グループの他の参加者の方の話を受け止めたり、助言したりして、どのグループも円滑なコミュニケーションをとりながらワークを進めていました。講師である広島県公民館連合会事務局長の河村さんが、演習全体のファシリテーションを行い、進行の仕方や参加者への言葉がけなどファシリテーターのモデルとなりました。
その後の講義では、演習で学んだファシリテーションについて、ファシリテーターの役割や求められるスキルなどの話をしました。ファシリテート能力だけでなく、コーディネート能力やプレゼンテーション能力など、様々な能力を発揮することが重要であることを伝えました。
参加者からは、「職場だけでなく、普段の生活から役立つことが聞けた。」「毎日単々と仕事をしていたところがあったけれど、いろいろいなことに意識をもって仕事をしようと思った。」などの声がありました。
再犯防止×地方創生政策ワークショップ研修
研修のねらい
国と地方という所属・立場の異なる両者が一堂に介し、顔の見える関係性を構築するとともに、再犯防止や地方創生に資する取組に関してアイディアを模索・共有することで、相互の連携強化を図る。
受講者
広島県職員、広島市職員、東広島市社会福祉協議会委員、更生保護法人職員、法務省関係職員(23名)
| 日時 | 内容 |
|---|---|
|
1月29日(水) |
○説明 ○ワークショップ ※研修の企画立案、当日運営で支援を行いました。 |





生涯学習センターの社会教育主事が支援しながら、広島矯正管区の担当の職員と一緒に 「ワークショップ型研修」の企画立案・運営を行いました。
昨年度は、中国地方で山陰・山陽の2会場に分けて実施されました。今年度は、昨年度からバージョンアップして、中国地方の各県で5会場に分かれて開催し、広島会場が今年度最後の開催となりました。
進行により、はじめに五つのグランドルールを確認した後、自己紹介とアイスブレイクを行いました。アイスブレイクは、「新聞紙タワー」を行い、どのグループが一番高く新聞紙タワーを作ることができるか競いました。グループの皆さんで知恵を出し合い、協力してタワーを作り、優勝したチームは、中国5県で一番高い、190cmの新聞紙タワーを作りました。
アイスブレイクで場の雰囲気が和んだところで、いよいよグループワークです。テーマ「広島県の再犯防止PRを考えよう」について、まず各自で付箋に考えを書き、その後グループで意見交流をしながら、再犯防止PRの取組案をつくりました。参加者の皆さん自身の経験や職場のある地域の資源を活用しながら、どのようなPRが考えられるか、熱心に協議が進められました。「それいいね」「これとこれをコラボしたら面白そう」など、それぞれのアイディアを十分共有しながら、終始楽しく和やかにワークショップが進められました。今後も、この協議でのつながりを生かして、より多くの地域の方に理解をしていただきながら、再犯防止に向けた取組を進めていかれるそうです。

















